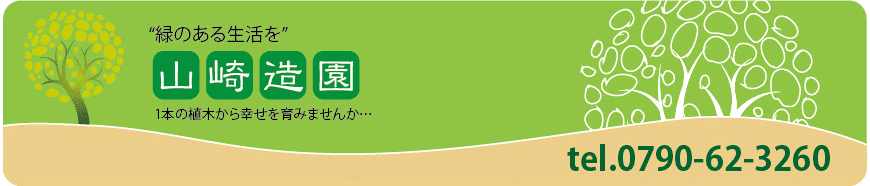トップページ > 季節の花・ガーデニングを楽しむ
1月 長寿・幸福を祝う 『福寿草(ふくじゅそう)』

 黄金色や橙色の花を咲かせる 福寿草(ふくじゅそう)は、
新年が明けたまだ寒い冬時期に雪の地面から顔を出すように咲きはじめます。
黄金色や橙色の花を咲かせる 福寿草(ふくじゅそう)は、
新年が明けたまだ寒い冬時期に雪の地面から顔を出すように咲きはじめます。
葉は細羽状で、背丈は3~5cmほどの小さな花です。
福寿草(ふくじゅそう)の開花
むか~し昔は、山や田んぼのあぜ道などで自生の群生を見れたそうですが、現代の福寿草は植栽されたものが大半です。
地域によっては1月下旬頃から開花が見られ、
屋外に植えてあるものは1月~3月下旬頃まで咲いています。
向きを変える福寿草の蕾(つぼみ)
 福寿草(ふくじゅそう)は、早春に咲く春を告げる花です。
福寿草(ふくじゅそう)は、早春に咲く春を告げる花です。
福寿草は咲き方に特徴があります。
日が当たる昼間に開花し、夕方には花を閉じ、昼間でも日がさえぎられると数分で花がしぼみ、
曇りだと花を閉じてしまい、雨の日には花が開きません。
開閉を繰り返しながら2~3週間咲き続けます。
つぼみの時期には太陽の光が当たる方向に向きを変える姿も愛らしく、じっくり観賞したい花です。
縁起の良い正月の花・元日草

福寿草(ふくじゅそう)を正月に飾る風習は江戸時代初期からあり、 「幸福」と「長寿」を合わせたその漢字の意味からも縁起の良い正月の花として使われます。
ミニ門松に添えられているのもよくお見かけします。
旧暦の正月(二月)頃に咲き出すことから新年を祝う花として、別名:元日草
(がんじつそう)とも呼ばれています。
めでたい花・福寿草(ふくじゅそう)
![]() 福寿草は、キンポウゲ科 の多年草です。
福寿草は、キンポウゲ科 の多年草です。
『キンポウゲ 』を漢字にすると『 金鳳花 』と書きます。おめでたい祝いの字を持つ花です。
長寿の祝い品などにも福寿草(ふくじゅそう)の花が選ばれてることが多いです。
寒中見舞いの風物詩
 福寿草(ふくじゅそう)は、
初春の花として寒中見舞いの絵ハガキなどにも使われています。
福寿草(ふくじゅそう)は、
初春の花として寒中見舞いの絵ハガキなどにも使われています。
古くから日本人の心をなごませる春の訪れを告げる祝いの花です。
福寿草を植える場所
福寿草(ふくじゅそう)を地植えする場合、午前中は日が当たり午後は日陰になる場所を選びます。 日当たりがよいのがいいと、夏場に乾燥するような場所に植えても上手く育ちません。 落葉樹の下などが向いています。

福寿草は、種から育てる場合、花が咲くまで4~5年は掛かる花です。福寿草は地域の人達に見守られ大切に育てられています。

地域景観
減少する福寿草の自生地
厳しい冬の終わり、まだ緑が少ない時期に小さい黄色の花が一面に咲く景観に足がとまります。
昔は福寿草の野生が群落をなしていた地域も多かったのですが、今は人の手で植えられるようになりました。地域によっては福寿草を保護しようと囲いを作ったりして守っているところもあります。
![]()
山崎造園では、お庭の手入れはもちろん、季節にあった花の植え替え・造園設計・施工、エクステリア・外構工事・造園土木・公共緑化工事、 剪定、移植、建物周辺の外構工事、公共施設の緑化工事、街路樹や道路、河川等における並木の整備も承っております。
荒地や畑の改良、緑化景観づくり、遊休農地や森林を活用した植栽など、傾斜地の整備から刈込、薬剤散布など、季節に応じた植栽管理も行います。
春を告げる花、福寿草(ふくじゅそう)やセツブンソウ(節分草)の植栽についてもお気軽にご相談ください。
2月~3月 宍粟市周辺の見どころ
宍粟市は兵庫県中西部に位置し、地域の人々により守り育てられている“豊かな自然”や、
四季折々の花が咲き誇る“花の名所”が各地にあります。
宍粟市のおすすめ観賞スポットにも是非訪れてください。
三椏(ミツマタ)の群生地
黄色い花でいっぱいの斜面

本谷のミツマタ(ほんだにのみつまた)
宍粟市一宮町東河内(ひがしごうち)の「坂の辻峠」(スギ林の中の急斜面の中)に、
ミツマタの群生地があります。
ミツマタは和紙などの原料になる植物で、黄色い花を一斉に咲かせます。
「ミツマタ」という名は、枝が一か所から三本に分かれるためにその名がついています。
球状に集まった小花からは甘い香りが漂い、
満開の3月頃には多くの方が観賞に訪れています。
・ 見ごろ:2月下旬~4月上旬
・ 場所:宍粟市一宮町東河内
・ 詳しくは→本谷のミツマタ
(西播磨ツーリズム振興協議会のホームページ)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|