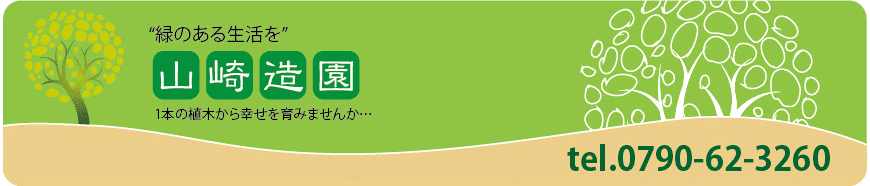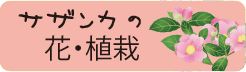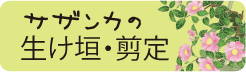トップページ > お庭造りのアドバイス・緑のある空間
サザンカの生垣があるお庭・樹形・特徴・植え付け・剪定・手入れ・育て方

サザンカ(山茶花)は、日本原産のツバキ科の常緑広葉樹(じょうりょくこうようじゅ)です。一年を通して葉をつけています。晩秋から3月にかけてツバキ(椿)に似た花を咲かせ、枝葉が密に茂り庭植えや生け垣として利用されています。花の色はピンクを基調に、薄紅色や艶やかな紅色や白色、絞り模様や斑入りなど色合いが豊富です。
(サザンカの植栽)

山茶花の名前の由来・茶室の床に飾る花・茶花(ちゃばな)
サザンカ(山茶花)は、古くから茶花(茶室の床に飾る花)として親しまれています。サザンカの名前の由来は、「山のお茶の花」を意味する「山茶花(サンサカ)」から転訛(てんか)して「サザンカ」と呼ばれるようになったという説が有名です。
(サザンカの生垣)

また、サザンカは唯一日本で発見されたツバキ属の植物で、日本固有の冬の花として国際的にも知られています。
和風庭園や公園、公共施設の庭、神社など身近なところで植えられています。
(サザンカの生垣)

生垣と垣根の違い
生垣と垣根は、どちらも庭に設置する囲いや仕切りのことで、混同(こんどう)して使われることもありますが、生垣(いけがき)は、生きた植物を並べて造ったもので、垣根(かきね)は、竹や木材などで造ったフェンスや仕切りの事です。一般的に敷地の境界に植えた塀の役割を果たすものを総称して「垣根」と呼ばれていますが、「垣根を剪定する」とはいわれません(;)。

生垣の種類、「外垣」と「境栽垣」
生垣(垣根)の種類は高さや用途で呼び方があります。外周に設ける高さ1.5~2mくらいの生垣を「外垣」(そとがき/がいえん)といい、敷地内の境界に高さ50cm~1mくらいの低木を帯状に植えたものを「境栽垣」(きょうさいがき)といいます。サザンカ(山茶花)は、外垣、境栽垣のどちらにも利用できる花木です。
(サザンカの生垣、「外垣」)

(サザンカの生垣、「境栽垣」)

サザンカの性質、「立ち性」と「横張り性」
サザンカ(山茶花)の種類は、大きくわけて「サザンカ系」「カンツバキ系」「ハルサザンカ系」に分類され、性質は「立ち性(たちせい)」と「横張り性(よこばりせい)」があります。
(写真:立ち性のサザンカの生垣)

「立ち性(たちせい)」は、サザンカ系に多く見られる性質で、枝が上に向いて伸び、庭木や大型の生垣向きです。サザンカの多くは立ち性(たちせい)です。
「横張り性(よこばりせい)」は、カンツバキ系のサザンカに多く見られる性質で、枝が重なり合うように横へ向いて伸び、背丈が低めで広がるように成長します。低木の生垣(境栽垣)や樹木の株元など、庭の一角に単体で育てる際にも適しています。
(写真:横張り性のサザンカ)

立ち性のサザンカ |
横張り性のサザンカ |
|
 |
 |
|
| 系統:サザンカ系 性質:立ち性が多い 開花時期:10月~12月 |
系統:カンツバキ系 性質:横張り性が多い 開花時期:11月~3月 |
|
| サザンカ系のサザンカは、早咲き品種です。多くは立ち性で、背丈が2~6mにもなり大きく育つ品種です。庭木や公園樹としてはもちろん、敷地内を区切る生垣きにも使われています。 | カンツバキ系のサザンカは、晩秋から冬に咲く品種です。多くは横張り性で、枝が横に広がるように育ち、背丈が低めでコンパクトに育てられます。中庭の一角やの花壇にも使われています。 |
(※但し、カンツバキ系のサザンカの中にも立ち性の品種もありますので、全てのカンツバキ系が横張り性というわけではありません。)
(サザンカの生垣)

(横張り性のサザンカ)

「横張り性」のサザンカは、背丈が低めです。単体で仕立てたり、中庭の一角や低い生垣向きです。
生垣に適した樹木・花木、「常緑樹」と「落葉樹」の違い
生垣に使用する樹木を選ぶ際、「常緑樹」か「落葉樹」かで、その後の手入れや仕立て方などが違ってきます。
目隠しを重視する場合は常緑樹が適しています。四季折々の変化を楽しみたい場合は落葉樹が好まれます。
(写真:常緑樹のサザンカ、撮影3月)

・常緑樹の生垣
「常緑樹(じょうりょくじゅ)」は、一年中葉が茂っているため、目隠しや防風効果が通年持続します。
(常緑樹、サザンカの生垣)
 「常緑樹」で生垣き向きの樹木は、サザンカ(山茶花)のほかにも、串団子のような実がつく マキノキ や、オレンジ色の花が咲く キンモクセイ などは、年中緑の葉があり、密に枝葉が茂り目隠し効果があります。
「常緑樹」で生垣き向きの樹木は、サザンカ(山茶花)のほかにも、串団子のような実がつく マキノキ や、オレンジ色の花が咲く キンモクセイ などは、年中緑の葉があり、密に枝葉が茂り目隠し効果があります。
・落葉樹の生垣
「落葉樹(らくようじゅ)」は、冬に葉が落ちるため、一時的に目隠し効果は薄れますが、その分、季節の変化を楽しめます。
(落葉樹、ドウダンツツジの生垣)
 「落葉樹」で生垣き向きの樹木は、春に花が咲いて赤い実がつく ハナミズキ や 真っ赤に紅葉する ドウダンツツジなどは、密度の高い小枝が形成され、落葉している冬期でも目隠し効果があります。
「落葉樹」で生垣き向きの樹木は、春に花が咲いて赤い実がつく ハナミズキ や 真っ赤に紅葉する ドウダンツツジなどは、密度の高い小枝が形成され、落葉している冬期でも目隠し効果があります。
生垣の作り方・植える間隔
敷地内に生垣を造成する際、植える間隔を詰めすぎると窮屈(きゅうくつ)になり、間隔を離しすぎると隙間が目立ちます。
生垣のサザンカ(山茶花)を植える間隔は、30cm~50cm程度あけることが一般的です。中型の生垣にする際は間隔を1mあける場合もあります。植える間隔は、この先の手入れにも大きく影響してきます。とても重要なポイントになります。
(サザンカの生垣の間隔)

サザンカの生垣・花びらじゅうたん
サザンカ(山茶花)の開花は、品種によって異なりますが、一般的に秋咲き種は10月から咲き、遅咲き種は12月から咲きだし、約2か月の間次々と咲きます。サザンカのもう一つの見どころは、散り際の美しさです。サザンカは花びらが1枚ずつ舞い散り、庭の風景に優雅さを添え、散っていく姿まで楽しめる花木です。 散った花びらじゅうたんのサザンカを見るのが楽しみという方も多くおられます。
(サザンカの生垣、花びらじゅうたん)

サザンカの生垣の剪定時期、花後の「強剪定」と初秋の「軽剪定」
サザンカ(山茶花)の生垣の剪定に適した時期は、花後の強剪定と、成長が進む9月頃にも軽い剪定を行い生垣の形を整えます。
サザンカの新枝は春に伸び、伸びた枝に花芽が付きますので、9月以降に多くの枝を切り落とすと、花芽を切ってしまうため注意します。花をたくさん楽しみたい場合は、夏以降の剪定は控えめに行い、不要枝を軽く間引く程度に留めておきます。

(サザンカの枝先)

サザンカの刈り込み剪定は、高さや幅などの樹形全体を整えるためにバッサリ切り揃える作業です。刈り込むと枝先が密生して新芽が密に芽吹きます。
サザンカの樹高を低くしたいなどコンパクトに仕立てる際は、切り戻し剪定をします。小枝を多く造る際や伸びすぎた枝を途中で切って形を整えたり、樹冠の大きさを調整する場合に行う剪定方法です。
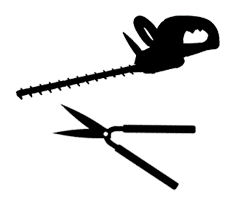 |
・刈り込み剪定サザンカの花が終わった直後から3月頃の剪定では、全体の形を整える「強剪定」を行います。この時期は花芽がまだ形成されていないため、花芽を落とす心配がなく剪定に適した時期です。主に刈込鋏や電動の生垣バリカンで表面の輪郭を刈りそろえます。 |
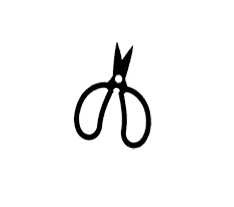 |
・間引き剪定サザンカの成長が進む9月頃の剪定は、込み合った枝を間引き不要な枝を取り除く「軽剪定」を行います。風通しを良くすることで病害虫の発生を防ぐことができます。主に植木鋏や剪定ばさみ(剪定鋏)を用いて透かしていきます。 |
サザンカの生垣の小枝づくり
ブロック塀だったところを「生垣にしたい」というご相談も近年多くなりました。サザンカの中でもカンツバキ系のサザンカは、枝が密に茂り、目隠し用の生垣にもよく使われる花木です。
ただし、サザンカは成長につれて下枝がなくなる傾向があり、小枝を多くしていきます。
(サザンカの生垣の株元)

(サザンカの生垣、内部の枝)

サザンカの生垣、小枝づくり
サザンカは、低い位置に小枝が付きません。サザンカを生垣にする際はその性質を活かして内部の小枝を密に育てます。
生垣の剪定方法、刈り込み剪定と間引き剪定
生垣の剪定には、「刈り込み剪定」と「間引き剪定」の2つの方法があり、刈り込みで形を整え、内部を間引いて風通しを良くします。サザンカの生垣は、樹形を整える刈り込み剪定と間引き剪定を組み合わせるのがポイントです。
(サザンカの生垣)

サザンカ(山茶花)の刈り込み剪定は、生垣全体を一定の形に整えるために行います。外側の葉や枝を剪定することで、見た目が整い、生垣らしい仕上がりになります。
間引き剪定は、内部の風通しを良くする目的で行います。密集した枝を間引くことで、病害虫の発生を防止する効果もあります。
(サザンカの生垣、長方形の樹形)

サザンカの円形の樹形・生垣・樹形づくり
円形の樹形は、自然にできるカタチではなく、人工的につくります。サザンカの生垣の表面を、電動バサミなどを使って整え、枝が伸びてきたら小まめに剪定を行い、樹形を一定のカタチと大きさで維持していきます。
(サザンカの生垣、丸い樹形)

(サザンカの丸い樹形の生垣)
 丸い生垣づくり
丸い生垣づくり
 サザンカ(山茶花)の生垣の樹形づくりは、花後~3月下旬頃までに強剪定を行い、形を整えていきます。
サザンカ(山茶花)の生垣の樹形づくりは、花後~3月下旬頃までに強剪定を行い、形を整えていきます。
サザンカの性質、園芸品種・系統・分類
サザンカ(山茶花)は、園芸品種が300種類以上もあり、開花時期・性質などの違いから大きく3つの品種群に分けられます。
(枝が上に向いて伸びる、立ち性のサザンカ)

樹形は一概ではないですが、サザンカを庭木として大きく育てる場合は、自生種に近い性質のサザンカ群の品種が向いています。小ぶりで低く育てたい場合は、横張り性の性質を持ったカンツバキ群の品種が向いています。
サザンカ群
サザンカ群は、サザンカの自生種に近い品種。小高木。特徴は、立ち性が多い。枝が上に向いて伸びる性質。開花時期:10月~12月
カンツバキ群
カンツバキ群は、寒椿から作出された小型の品種。低木。特徴は、横張り性で、枝が重なるように伸びて横へ広がる性質。開花時期は11月~2月
ハルサザンカ群
ハルサザンカ群は、サザンカとヤブツバキの交雑。サザンカに近い品種とツバキに近い品種がある。小高木。開花時期は12月~4月
日本原産のサザンカ(山茶花)
サザンカ(山茶花)は日本を原産とするツバキ科の植物で、主に本州の山口県、四国、九州などで自生が見られます。
サザンカというとピンク系の花色が特徴ですが、サザンカの原種は白い一重咲きで秋咲きです。葉は小さく幅が狭く、新葉には赤みが見られることがあります。

自生種に近いサザンカの多くは立ち性です。

サザンカの生垣に適しているサザンカとツバキの交雑種「寒椿(かんつばき」の特徴
サザンカの「寒椿(かんつばき)」は、サザンカとツバキの交雑種で、横に広がるように伸び、背丈が高くなりにくい性質を持っています。枝葉の密度が高く、サザンカの品種の中でも生垣に適しています。また、花期が長く次々と花が咲きます。
(低木の横張り性サザンカ、カンツバキ群)

(低木の横張り性サザンカ、カンツバキ群)

 ツバキ科の樹木に注意!刺す毛虫、チャドクガ(茶毒蛾)
ツバキ科の樹木に注意!刺す毛虫、チャドクガ(茶毒蛾)
ツバキやサザンカの葉っぱに毛虫!?
ツバキ科の植物には、葉を食い荒らす毛虫「チャドクガ」が付着することがあります。チャドクガは毛に毒性があるため、被害を防ぐためには発生初期に幼虫ごと駆除することが重要です。特に春から秋にかけては、害虫の発生が多い季節です。サザンカを剪定する際は、手袋と防護メガネも必須で備えて行います。
 チャドクガ
チャドクガ
チャドクガ(茶毒蛾)は、チョウ目ドクガ科の昆虫で、毒ガの一種です。幼虫には数十万本の 毒針毛(どくしんもう)があり、刺す毛虫です。
 チャドクガの毛が肌に触れると、ひどいかゆみや強烈な痛みが走り、皮膚炎を引き起こします。毛虫の毛は風で飛んでくることもあるため、風向きにも注意が必要です。発見した場合は駆除してから作業を行います。
チャドクガの毛が肌に触れると、ひどいかゆみや強烈な痛みが走り、皮膚炎を引き起こします。毛虫の毛は風で飛んでくることもあるため、風向きにも注意が必要です。発見した場合は駆除してから作業を行います。
 根腐れ?!水のやり過ぎ、葉が黄色くなってきた
根腐れ?!水のやり過ぎ、葉が黄色くなってきた
サザンカの葉っぱが黄色くなってきた・・・?!
サザンカ(山茶花)の葉が黄色くなってきた原因の一つに「根腐れ」や「日当たり不足」、「気温差」などが考えられます。特に日陰で育てているサザンカの場合、過剰な水やりは根腐れの原因になります。対策としては、光線の確保、多湿にならないように管理するなどで予防できます。

サザンカの水やり
 地植えのサザンカは、苗を植え付けてから2年は根を育てるために、地面が乾いたらたっぷりと水を与えます。根付いたら頻繁に水やりする必要はありません。降雨に任せても育ちます。ただし夏は注意が必要です。真夏の水やりは、朝と夕方の時間帯に水をたっぷりと与え、昼の炎天下は避けます。
地植えのサザンカは、苗を植え付けてから2年は根を育てるために、地面が乾いたらたっぷりと水を与えます。根付いたら頻繁に水やりする必要はありません。降雨に任せても育ちます。ただし夏は注意が必要です。真夏の水やりは、朝と夕方の時間帯に水をたっぷりと与え、昼の炎天下は避けます。
また、開花期の秋から冬にかけては、水やりが重要です。花が咲き終わってから冬場は、成長がやや抑えられるため、水やりを控えめにします。
 黒い病斑?!縁から枯れる「炭疽病(たんそびょう)」
黒い病斑?!縁から枯れる「炭疽病(たんそびょう)」
サザンカの葉っぱに黒い点の斑?!縁が黒く枯れてきた・・・?!
サザンカ(山茶花)は比較的丈夫な植物ですが、「炭疽病(たんそびょう)」の発生が見られることがあります。炭疽病はカビの一種で伝染病です。葉に円形から楕円形の黒い病斑を形成し、縁(ふち)から枯れるように広がっていきます。予防策としては、剪定で風通しを良くし、湿気がこもらない環境にすることも有効です。

炭疽病(たんそびょう)
 サザンカの葉に黒い小型円形病斑が発病した際は、早めに取り除き、必要に応じて殺菌剤を散布します。
サザンカの葉に黒い小型円形病斑が発病した際は、早めに取り除き、必要に応じて殺菌剤を散布します。
 炭疽病(たんそびょう)の黒い点のような斑は、縁(ふち)から枯れるように広がっていきます。
炭疽病(たんそびょう)の黒い点のような斑は、縁(ふち)から枯れるように広がっていきます。
サザンカやウメ、アジサイ等、多くの植物に発生する伝染病です。

感染した部位はできるだけ早めに取り除き、殺菌剤を散布します。
被害が全体に広がっている場合は、切り戻し剪定で風通しを良くします。被害が株全体に発病した場合は、被害株を除去します。
 剪定時期の失敗、花芽を切った?花がほとんど咲かない?!
剪定時期の失敗、花芽を切った?花がほとんど咲かない?!
秋になっても、サザンカの花芽がほとんどつかない・・・?!花付きが悪い?
サザンカ(山茶花)に花がつかない場合の多くは、剪定の時期が間違っていることが原因です。
(花がほとんど咲かないサザンカの生垣)

(サザンカの花芽がついていない枝)

花芽を切った枝
 サザンカの剪定を夏以降に行うと、花芽を切り落としてしまう為、花がほとんど咲きません。
サザンカの剪定を夏以降に行うと、花芽を切り落としてしまう為、花がほとんど咲きません。
逆に、花をあまり咲かせたくない場合や散る花びらを減らしたい場合は、夏以降に花芽を切り落とすこともあります。
(サザンカの花芽とつぼみ)

サザンカの花芽
サザンカの花芽は、春に伸びた枝の先端と葉腋(ようえき、葉のつけね)に、花芽が形成します。サザンカの剪定は花が終わった後から3月頃までに行うのが理想です。
 枝が伸びるサザンカの生垣、樹形が乱れてくる・・・?!
枝が伸びるサザンカの生垣、樹形が乱れてくる・・・?!
生垣の枝の手入れ、自然な風合いにしたい。
サザンカ(山茶花)の性質には、立ち性と横張り性があり、枝が上に向いて伸びるのは立ち性のサザンカです。
立ち性のサザンカは枝が上に向いて伸び庭木向きですが、生垣にも活用できます。性質をいかした自然な風合いの生垣にすると引き立ちます。
(密集した枝、立ち性のサザンカ)

(密集した枝、立ち性のサザンカ)

立ち性サザンカの生垣
立ち性のサザンカを生垣風に育てると、枝が不均等に上に伸びて樹形が乱れることはよくあります。

 サザンカの剪定は花後から3月頃が適期ですが、密生して風通しが悪い場合は、剪定時期以外でも、蕾(つぼみ)が付いていない枝や枯れ枝を切って風通しをよくしておきます。
サザンカの剪定は花後から3月頃が適期ですが、密生して風通しが悪い場合は、剪定時期以外でも、蕾(つぼみ)が付いていない枝や枯れ枝を切って風通しをよくしておきます。
 サザンカの下枝がスカスカ?!
サザンカの下枝がスカスカ?!
サザンカの生垣の下枝がスカスカになった・・・?!下枝を隠すのに良い植物は?
庭の仕切りに低木を並べるなど、サザンカの生垣は幅広く活用できます。サザンカの生垣の下枝が伸び、スカスカになる場合は、切り戻し剪定を行うのも一つの方法ですが、他の植物を周囲に植えることで見た目を改善できます。
(写真:サザンカの下枝が伸びた姿、撮影2月)

スカスカの下枝と組み合わせる植物
 下枝が長く伸びたサザンカの生垣と他の植物を組み合わせる場合、
例えば、春に咲くチューリップやスイセン、夏に咲くポピーや百合(ユリ)を近くに植えると、サザンカの花がない時期に庭が華やかになります。
下枝が長く伸びたサザンカの生垣と他の植物を組み合わせる場合、
例えば、春に咲くチューリップやスイセン、夏に咲くポピーや百合(ユリ)を近くに植えると、サザンカの花がない時期に庭が華やかになります。
 サザンカの紅葉?冬に葉っぱが赤くなる・・・?!
サザンカの紅葉?冬に葉っぱが赤くなる・・・?!
常緑樹のサザンカの葉が、冬になると赤くなるのは葉焼け?病気?
サザンカ(山茶花)は常緑樹で年中葉がある花木ですが、冬に葉が赤くなる現象は珍しいことではありません。 冬の寒さ、気温の影響や霜がおりた後にも見られます。
(冬に葉が赤くなったサザンカの生垣)

(葉が赤色になったサザンカ)

サザンカの葉の変色
 サザンカ(山茶花)の葉は、冬に赤くなっても、気候が暖かくなると、葉の色は徐々に緑色に戻っていきます。
サザンカ(山茶花)の葉は、冬に赤くなっても、気候が暖かくなると、葉の色は徐々に緑色に戻っていきます。
 似ているツバキとサザンカ、生垣向きはどっち?
似ているツバキとサザンカ、生垣向きはどっち?
サザンカと ツバキ(椿)は、花も咲く時期も似ています。生垣向きはどっちがいい?
サザンカ(山茶花)は、日本原産の花木で、古くから生垣に利用されています。サザンカは、葉が小さめで刈り込み剪定にも強く、小枝が多く枝葉が密生し樹形が整いやすいです。
(横張り性のサザンカ、生垣向き)

ツバキ(椿)の中でも「ヤブツバキ」は生垣向き
 ツバキ(椿)も、日本原産の花木です。サザンカと比べると葉が大きめで背丈も大きく育ち、枝を透かすように整える花木です。ツバキ(椿)とサザンカでは、サザンカのほうが生垣に向いていますが、ツバキの品種の中でも刈り込みに強く茎も枝も細い「ヤブツバキ」は、生垣に適しています。
ツバキ(椿)も、日本原産の花木です。サザンカと比べると葉が大きめで背丈も大きく育ち、枝を透かすように整える花木です。ツバキ(椿)とサザンカでは、サザンカのほうが生垣に向いていますが、ツバキの品種の中でも刈り込みに強く茎も枝も細い「ヤブツバキ」は、生垣に適しています。
(ヤブツバキの生垣)

ツバキとサザンカの違い・見分け方
ツバキ(椿)とサザンカ(山茶花)は見た目が似ています。一見区別が難しいですが、花の散り方で見分けられます。サザンカは花びらが1枚ずつ散るのに対し、ツバキは花全体が落ちます。
開花期にも違いがあり、サザンカは秋10月から12月頃から咲きだし、花姿が平らに開きます。ツバキは冬1月から早春にかけて咲きだし、花の根元がつながっていて筒状です。
また、葉の特徴も異なります。サザンカの葉は薄く、小型で葉の縁のギザギザ(鋸歯(きょし))がハッキリしているのに対し、ツバキの葉は厚みがあり光沢のある質感で葉の縁のギザギザが浅いです。
(ツバキとサザンカの違い・見分け方)

 サザンカの枝はぐんぐん伸びます。サザンカを放置?窮屈に乱れた樹形を復活
サザンカの枝はぐんぐん伸びます。サザンカを放置?窮屈に乱れた樹形を復活
サザンカ(山茶花)の成長は比較的ゆるやかですが、枝は年30cmくらい伸びます。サザンカの剪定は年2回が基本です。
 ・1回目の剪定は、花後に枝を短く切り、全体を刈り込み樹形を整えます。
・1回目の剪定は、花後に枝を短く切り、全体を刈り込み樹形を整えます。
サザンカは、春に伸びた枝の先端に花芽が夏(6~7月)に形成しますので、初春(3月下旬頃、地域によっては4月頃)までには強剪定を済ませておきます。
・2回目の剪定は夏過ぎです。夏は害虫が発生しやすい時期ですので、繁茂した枝を軽く間引く程度の軽い剪定(弱剪定)を行い、樹形も整えます。
・その後は定期的に枯れた枝や細い枝、込み入った枝を間引き、風通しを良くし、適宜(てきぎ)軽い剪定を行い樹形を整えます。
枝がよく伸びる場合は、年3回の剪定を計画します。
 サザンカの枝が密に混み合う?!
サザンカの枝が密に混み合う?!
横張り性のサザンカは枝が混み合って、生垣の中が密になる・・・?!
繁茂する横張り性サザンカの枝
 横張り性のサザンカの生垣の内部は、枝が重なるように広がって伸び、内部の枝葉が混み合ってきます。とくに夏は害虫が発生しやすく枝を透くように剪定します。
横張り性のサザンカの生垣の内部は、枝が重なるように広がって伸び、内部の枝葉が混み合ってきます。とくに夏は害虫が発生しやすく枝を透くように剪定します。

生垣の混植、根詰まり?!
生垣の植栽スペースに色んな種類の生垣を植えていると根が詰まる・・・?
サザンカ(山茶花)の根は、地中に深く張っていきます。生垣の植栽スペースが狭いと根が張り合い、根詰まりを起こすことがあります。互いに養分を取り合うようになってしまうと、樹勢が弱わり、花付きも悪くなります。
(生垣の植栽スペース)

生垣の根切り
「根切り」は、土の中にスコップ等を使って樹木の根の先端を切ることです。根切りをすることで養分を吸い上げやすくなり、新しい芽がたくさん出てきます。ただし、根を切るのは細い根です。深く根切りをすると倒れる原因になります。
サザンカの根切りを行う時期は、発根しやすい花後に行います。移植する際もこの時期が適期です。
※生垣に 「根切り」をするのはサザンカだけではありません。株が大きくならないように細根を切って成長を制御しています。
 サザンカの摘蕾(てきらい)、つぼみ摘み、開花数を減らす
サザンカの摘蕾(てきらい)、つぼみ摘み、開花数を減らす
サザンカの花が多い、付き過ぎ・・・?
サザンカ(山茶花)の摘蕾(てきらい)は、花数を調整して樹勢を保ち、生育をよくするために、つぼみを摘み取る作業です。
サザンカは、花を付け過ぎると樹勢が弱ったり、その後の成長がおそくなったり、全体的に小ぶりになることがあります。
(沢山のつぼみが付くサザンカ)

サザンカの摘蕾(てきらい)・つぼみ取り
たくさん蕾(つぼみ)が付いたら、大きくなる前に余分な蕾(つぼみ)を適度に摘み取って栄養を枝や葉に行き渡らせると生育を助けられます。
(※蕾(つぼみ)を摘み取ることを摘蕾(てきらい)といいます)

沢山の花を咲かせる山茶花の手入れ
サザンカ(山茶花)の花芽は、春から新しく伸びた枝の先端近くに6~7月頃に付きます。沢山の花を咲かせるには新しく伸びる枝を増やしていきます。
(たくさん花を咲かせているサザンカの生垣)

(たくさん花を咲かせる剪定)
沢山花を咲かせる方法
沢山の花を咲かせる方法は、剪定と肥料やりです。花後の強剪定で、株全体の枝を切って小枝を増やし、花芽が形成された枝を切らないようにすると、秋から冬には次々と沢山の花が咲きます。また、花後の剪定時に肥料を与えることで、翌年の花つきを良くします。
サザンカの肥料やり、寒肥作業
サザンカ(山茶花)の肥料やりは、施肥(せひ)と追肥(ついひ/おいごえ)で成長を施し、美しい花を咲かせます。
肥料やりの時期は、早咲きの山茶花は、1月~2月に寒肥として有機質肥料を株元に埋め、冬を越えるための栄養を与えます。遅咲きの山茶花は、3月と9月頃に肥料やりを行います。(開花中は肥料を与えません。) 開花が終わった後に追肥(ついひ/おいごえ)を行い、来年の花付きを良くします。サザンカは、肥料の過不足に敏感な性質があります。肥料を過剰に与えすぎないよう注意します。


寒肥(かんごえ、かんぴ)は、庭木(植木)に肥料を与える作業です。 土に栄養分を補充し花つきを良くします。
サザンカの生垣に追肥を行う際は、株元から30~50cm程度離れた場所に浅い溝を掘り、掘った溝穴に肥料を肥料をまき、軽く土をかぶせます。(※注意、必要以上の肥料のやり過ぎは枯れる原因にもなります)
サザンカの増やし方と植え替え時期
サザンカ(山茶花)は挿し木で増やすことができます。挿し木の最適な時期は春から初夏の6月~7月、または秋頃が適しています。
サザンカの「挿し木」をする方法は、健康な親木から10cm程度の枝を切り取り、下葉を取り除いて清潔な用土に挿します。市販の挿し木用土などを使用すると発根しやすくなります。
挿した土を十分に湿らせ、直射日光を避けた明るい日陰で水切れしないように管理します。2~3週間すると発根が始まります。発根を確認したら鉢上げを行い苗木に仕立てます。
また、サザンカは種(タネ)から増やすこともできます。花後に果実ができます。秋になると開きます。暗褐色の種子を採取したらすぐにまきます。
(サザンカの果実)

サザンカを植える場所
庭植え(地植え)のサザンカを育てる適切な環境は、風通しが良く、水はけの良い直射日光を避けた明るい日陰の場所を選びます。中庭など建物の陰ができる半日陰の場所でも育ちます。サザンカはやや湿気を好みますが、過湿になると根腐れを起こします。
(サザンカの植栽)

サザンカの春夏秋冬、季節の手入れ
サザンカ(山茶花)の生垣は、季節ごとの手入れを工夫していきます。春3月中旬にもなると成長が活発になり、4月~5月上旬頃は新芽がぐんぐん伸びる時期です。剪定と追肥を行うことで成長を促します。
(サザンカの芽吹き(めぶき)、撮影3月)

(サザンカの新芽)

夏は水不足に注意する時期です。花芽は春から伸びた枝に6月頃に付きます。サザンカの剪定は、特に春先(3月頃~遅くとも4月)と、夏を過ぎ花が咲く前の9月にも軽く剪定を行うことが推奨されます。花が咲く前に枯れた枝や細い枝を間引くことで風通しを良くし病害虫の被害を抑えます。
秋10月から冬にかけては開花期となる時期です。開花中の乾燥を防ぐため適度な水管理を行います。
花の終わり
花後に寒肥として有機質肥料を与えます。剪定などの大きな手入れは、花が終わってから行います。
(サザンカの手入れ・花の終わり)

サザンカの株立ち樹形
サザンカ(山茶花)は庭園や公園など公共の庭など、通路の側面にも植栽されることが多い樹木です。サザンカの仕立て方は、太い幹が1本の一本立ちの樹形や、株の根元から複数の幹が伸びる株立ち樹形、どちらでも育てることができます。
(株立ち樹形のサザンカ)

サザンカの樹形
主幹が1本で幹の途中から枝分かれした樹形のサザンカ(山茶花)は、丸みのある樹形に仕立てるとカタチが整います。庭園や公園など広い敷地で管理しているものは自然な枝ぶりを活かした樹形を保ち高さ2m~5m程の高さで維持していきます。
(卵型樹形のサザンカ)

(丸みのある樹形のサザンカ)

(一本立ち樹形のサザンカ)
一本立ちは、根元から一本の主幹が伸びた樹形です。一本立ち樹形のサザンカは株元がスッキリとした印象があります。低木の植物と組み合わせると冬の庭が華やかになります。
背丈のある大型のサザンカの生垣
サザンカ(山茶花)は剪定による生垣の形成も容易です。背丈のある生垣にも仕立てることもできます。常緑性と程よい密度の枝葉から、プライバシーを保ちつつ防風や防音効果を発揮します。
サザンカを大型の生垣にする場合、高さを1.5m~2mほどに揃えると、美しい仕上がりになります。また、広い庭や壁面のような生垣として使用する場合、高さが2m~6m程になる品種が適しています。サザンカは剪定によって形状を整えやすく曲線や直線など好みの形状に仕立てることができます。
(背丈のある大型のサザンカの生垣)

サザンカの苗木の植え付け・植栽
サザンカ(山茶花)は弱酸性の土壌を好みます。植え付ける際に酸性度の高い腐葉土やピートモスを混ぜ込みます。苗木の植え付けは、新芽が発芽する前に行います。植え付け時期は、3~4月、9月中旬~10月が適しています。この時期の植え付けは、気候が安定しているため根付きやすくなります。植え付け時に堆肥(たいひ)をしっかり混ぜ込むことで、長期間健康的に育ちやすい環境が整います。
| 立ち性サザンカ | 横張り性サザンカ | |
 |
 |
|
サザンカ系園芸品種の多くは、立ち性(たちせい)です。 特徴:立ち性のサザンカは高木になります。茎や枝が上に向いて伸びる性質で、庭木向きです。 |
サザンカの生垣は、横張り性(よこばりせい)の性質を持ったカンツバキ群のサザンカがよく使われます。 特徴:カンツバキ群のサザンカは低木です。茎や枝が横へ広がるように伸び、高くなりにくい性質で、庭の区切りにサザンカの低木を並べるなど幅広く活用できます。 |
サザンカがあるお庭
サザンカ(山茶花)の樹高は10m未満の常緑性小高木ですが、2階建ての家を超えるほど大きく育ちます。サザンカを小ぶりの樹形で育てたい場合は、切り戻し剪定を行い、樹形を一定の大きさで保つことができます。これ以上大きくしたくない高さで芯止めもできます。
(サザンカがあるお庭)

![]()
山崎造園では、造園設計・施工、エクステリア・外構工事・造園土木・公共緑化工事はもちろん、 戸建て住宅の緑化工事、料亭や茶室や庭園の園路、玄関周辺の階段工事、塀の設置や撤去、生垣の植栽・維持管理、肥料やり、害虫予防・消毒など、庭木(植木)の1本の剪定から承っております。
サザンカ(山茶花)は大きく育ちます。手入れが困難な高所作業や傾斜作業もお気軽にご相談ください。
主要地域 :造園工事も対応いたします!
兵庫県宍粟市内(一宮町、山崎町、千種町、波賀町)、姫路市、たつの市、揖保郡、佐用郡、神崎郡、朝来市、福崎町、他、高砂市、加古川市、太子町、相生市、赤穂市、加西市、小野市、加東市、三木市、西脇市、明石市、播磨町、稲美町、市川町、神戸市)
横張り性のサザンカ(山茶花)
 2018.12.30
2018.12.30
園芸品種のサザンカ(山茶花)の多くは、茎や枝が上に伸びる「立ち性(たちせい)」ですが、丈が低めで樹形が横に広がる性質の「横張り性」のサザンカは、枝葉が密生して生垣に仕立てやすいです。
横張り性のサザンカは、真冬に花が咲くため、剪定は花後~3月下旬頃が適期です。
サザンカは、下枝がなくなる性質がありますが、横張り性(横に広がる性質)のサザンカは、幹の下部から分岐するのも特徴です。
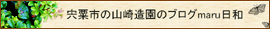 詳しくは、山崎造園のブログ「横張り性のサザンカ(山茶花)」の記事でも紹介しています。
詳しくは、山崎造園のブログ「横張り性のサザンカ(山茶花)」の記事でも紹介しています。
階段横の斜面に設けられた植栽スペースのサザンカ
 2016.12.30
2016.12.30
サザンカ(山茶花)はツバキ(椿)に比べ葉が小さめで密に付き、生垣にもよく用いられます。
サザンカの生垣が「下がスカスカな状態になっている・・・」というご相談もよくお聞きします。
サザンカやツバキ類は、成長すると下枝が殆んどなくなります。
「1本仕立て」の場合はその性質を活かすのですが、生垣の場合は下枝を作っていきます。
下枝の作り方
樹冠(じゅかん:上部で葉が茂っている部分)の勢いを抑え、 根元から出る枝(脇芽といいます)を伸ばすように剪定していき、 主枝と側枝を伸ばしていくと、その付け根からもまた脇芽(わきめ)を 出して下枝をつくっていきます。
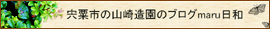 詳しくは、山崎造園のブログ「サザンカ(山茶花)の生垣」
の記事でも紹介しています。
詳しくは、山崎造園のブログ「サザンカ(山茶花)の生垣」
の記事でも紹介しています。
(サザンカの植栽)

(サザンカの枝先)

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|