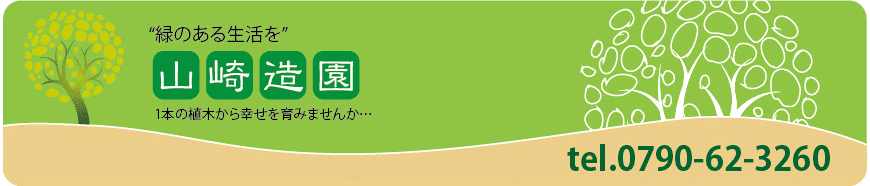トップページ > 季節の花・ガーデニングを楽しむ
ヤマボウシ(山法師)があるお庭、植栽・剪定・手入れ

ヤマボウシ(山法師)
ヤマボウシはミズキ科サンシュユ属に属する落葉高木で、高さは10~15mに成長します。学名は「Cornus kousa(コーナス コウサ) 」です。ヤマボウシの自然な樹形は、枝が横に広がる野趣あふれる姿です。

ヤマボウシがあるお庭
ヤマボウシは、初夏に花のように見える白い総苞をつけ、秋には赤い実がなり、紅葉も美しい落葉高木です。
ヤマボウシには、落葉性と常緑性があり、一般的なヤマボウシは、落葉性で、冬に葉を落とします。葉に丸みがあり、葉の縁に波が入っているのが特徴です。

花は、5月中旬から7月にかけて、白や淡いピンクの花を咲かせす。花びらのように見える部分は花を包んでいた「総苞片(そうほうへん)」と呼ばれる葉で、本来の花は中心部の球体に小花が集まっています。

ヤマボウシの満開期は、道行く人々の目を止めるほど咲き誇ります。日本では古くから寺院等で植えられており、庭木やシンボルツリーとしても親しまれています。公園や公共の庭など身近な場所でも植えられています。
(ヤマボウシがあるお庭)

花が終わると、総苞片(そうほうへん)は変色して枯れて散り、緑色の果実が膨らんでいきます。
(ヤマボウシの総苞片の終わり、撮影7月7日)

秋9月~10月頃になると果実が赤く熟します。
(ヤマボウシの実)

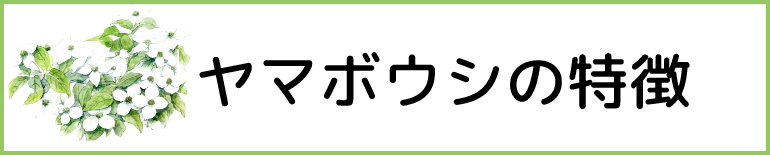
自然樹形が美しいヤマボウシ(山法師)
ヤマボウシ(山法師)は、山で咲いているかのような自然樹形が美しい樹木です。新緑、花、果実、紅葉、落葉、枝ぶり、四季折々の風情を楽しめます。
(ヤマボウシの株立ち樹形)

白い花びらに見えるものは、総苞片(そうほうへん)です。
ヤマボウシ(山法師)は、枝先の葉腋に花を付け、十字状に開く苞葉(ほうよう)が、花として観賞されます。苞葉(ほうよう)の1枚1枚を総苞片(そうほうへん)といい、4枚の総苞片(そうほうへん)が花びらとして見られています。
(開きはじめた花びらのような総苞片、撮影5月14日)

花を包んでいた総苞片(そうほうへん)は、5月中旬ころから開きはじめ、徐々に大きくなり、色が白くなっていきます。総苞片(そうほうへん)が開きはじめた頃の花(基部の球体に集まっている花)は、まだ開花していない蕾(つぼみ)の状態です。
 ヤマボウシの総苞片(そうほうへん)は、先が尖がっているのが特徴です。
ヤマボウシの総苞片(そうほうへん)は、先が尖がっているのが特徴です。
ヤマボウシ(山法師)の開花時期
「ヤマボウシの花が咲いた」という表現は、花びらのように見える総包片(そうほうへん)が開いた状態を言われます。
ヤマボウシ(山法師)は開花期間が長く、初夏の5月中旬頃から咲きはじめ7月上旬頃まで見ることができます。

ヤマボウシ(山法師)の花序(かじょ)の柄(え)は長く、短い枝から立ち上がって伸びます。
(ヤマボウシの花、うしろ姿)

ヤマボウシの見ごろは、5月下旬から6月中旬です。※気候や生育状況によって見頃の時期は前後します。

ヤマボウシは、緑色の葉と、白い総苞片(そうほうへん)のコントラストが美しく清楚な印象です。
ヤマボウシ(山法師)の花
ヤマボウシ(山法師)の本来の花は、中心部分にある黄緑色の球状の部分です。小さな花が20~30個密生して咲きます。
花が開くと、中心部が華やかになります。
球形の花序の一つひとつの花に雄しべと雌しべがあります。
 花のつき方
花のつき方
ヤマボウシのように複数の花が密に集まって一つのカタチを形成するつき方を、「頭状花序(とうじょうかじょ)」といいます。
ヤマボウシ(山法師)の名前 由来
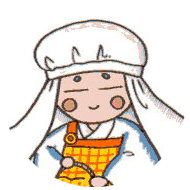 ヤマボウシの名前の由来には諸説ありますが、花に見える苞葉(ほうよう)の白い部分が僧侶の頭巾(法師)を連想させることから「山法師(やまぼうし)」と名づけられたとされています。
ヤマボウシの名前の由来には諸説ありますが、花に見える苞葉(ほうよう)の白い部分が僧侶の頭巾(法師)を連想させることから「山法師(やまぼうし)」と名づけられたとされています。
ヤマボウシ(山法師)の葉の特徴
ヤマボウシの葉は、先端が鋭く尖った丸型の卵形または幅広の楕円形で、付け根の基部は丸みを帯びています。葉脈がよく目立ち縁(ふち)が波打ってきます。

葉の縁(ふち)が細かく波打つ姿から、一見ギザギザの鋸歯(きょし)があるように見えるのですが、ヤマボウシの葉に鋸歯(きょし)はありません。
(葉のフチが波打つヤマボウシの葉)

ヤマボウシの葉の裏面は、側脈が出る分かれ目の脈腋(みゃくえき)部に黒褐色の毛のがあるのが特徴です。
(ヤマボウシの葉の裏面)

ヤマボウシ(山法師)の果実
ヤマボウシの果実は、多数の花が一つの実になった「複合果」です。丸い表面はデコボコしています。
総苞片(そうほうへん)が散ったあと、ヤマボウシの果実は緑色をしています。膨らみはじめた7月から8月頃の果実は上にむいていますが次第に垂れていきます。

ヤマボウシ(山法師)の果実・色付きはじめ
夏の終わりから秋の9月~10月になると、実(み)が徐々に赤く色づいてきます。

ヤマボウシ(山法師)の熟した果実は自然と落下します。
ヤマボウシ(山法師)の実は、観賞用としてだけでなく、食用としても楽しむことができます。
(赤く熟したヤマボウシの実)
 収穫適期
収穫適期
果実の収穫は、赤く熟してからです。生でも食べられます。マンゴーのような甘みがありフルーティです。ジャムや果実酒作りにも使われています。
(落下したヤマボウシの実)
 ヤマボウシ実の中には、種(タネ)が数個、1~4つか5つくらい入っています。タネから増やしたい場合は、熟した果実から種を取り出します。
ヤマボウシ実の中には、種(タネ)が数個、1~4つか5つくらい入っています。タネから増やしたい場合は、熟した果実から種を取り出します。
斑模様(まだらもよう)の幹
ヤマボウシ(山法師)の樹皮は、赤褐色~灰色で、樹齢を重ね成木になると、樹皮が剥がれて斑模様(まだらもよう) になります。 老木になると不規則に剥がれた灰色の模様が入り混じり、独特の風合いがあります。
(ヤマボウシの幹)

(ヤマボウシの枝)

 ヤマボウシの若い枝は、赤褐色を帯びています。
ヤマボウシの若い枝は、赤褐色を帯びています。
ヤマボウシ(山法師)の紅葉
ヤマボウシ(山法師)の実が落ちた10月頃、秋の紅葉の時期には葉が美しい橙色に染まります。
(写真:果実が落ちた後のヤマボウシの紅葉)

ヤマボウシの紅葉は、日の当たる場所と朝晩の寒暖差が激しいと、より赤く紅葉します。

「常緑ヤマボウシ」と「落葉性ヤマボウシ」の違い・見分け方
ヤマボウシには大きく分けて常緑性と落葉性の2種類があります。落葉性ヤマボウシは、春から夏に葉を茂らせ、秋には紅葉、冬には葉を落とします。
常緑ヤマボウシは一年を通して葉を保ち、葉に光沢があり、冬場に赤くなる傾向があります。

| 常緑ヤマボウシ | 一般的なヤマボウシ | |
常緑ヤマボウシは、常緑性で、年間を通して葉が茂っています。葉は細長く、光沢があり、葉の先端が尖っていてシャープな印象です。 原産地は中国南部です。 |
一般的なヤマボウシは、落葉性で、冬に葉を落とします。葉に丸みがあり、葉の縁に波が入っています。自然美が美しい柔らかい印象です。 原産地は日本・朝鮮半島・中国などです。 |
常緑ヤマボウシの紅葉
1年中葉をつけている常緑性のヤマボウシも、秋が深まると、葉に赤みが混じってきます。冬の寒さにあたると紫紅色になり、落葉性のヤマボウシとはまた違った深みのある紅葉が個性的です。春になると、葉は緑色に戻ります。


葉が紅色一色に染まった常緑ヤマボウシ


これは、常緑ヤマボウシ、コルヌス・ホンコンエンシスの月光Cornus hongkoongensis‘Gekkou’という品種です。常緑樹にはしばしば冬の寒い時期にこのように葉が赤くなることがあります。この、常緑ヤマボウシの特に‘月光’はよく冬に色づくようで、「冬紅葉」として観賞の対象にもなるようですね。(引用:神戸市立森林植物園ブログ)
ヤマボウシ(山法師)の自生
落葉性のヤマボウシ(山法師)の原産地は日本、朝鮮半島、中国です。日本では本州、四国、九州の低山の湿った林地に自生しています。

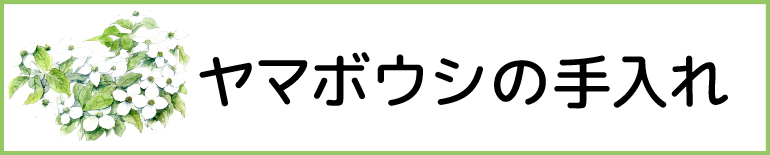
ヤマボウシ(山法師)がある庭
ヤマボウシ(山法師)の樹形は、幹から枝先に向かって先細りしていく自然の樹形が美しく、清楚で落ち着いた雰囲気があり、坪庭や茶室の庭園、和風のお庭にもよく合います。

ヤマボウシ(山法師)の仕立て方
ヤマボウシ(山法師)の枝は比較的柔軟性があり、成木になるにつれて横に広がるように成長します。そのため、単幹といった一本立ちや複数の幹で形成された株立ちにも仕立てることができますが、一本立ちは大きく育ちます。ヤマボウシの庭木のほとんどが株立ち樹形です。
 単幹樹形
単幹樹形
1本の木がそのまま立ち上がった一本の幹で樹形が作られるものを「単幹樹形」といいます。

株立ち樹形
株立ちは、地際(じぎわ)から数本の幹が伸びるような樹形です。涼しげな風合いでよりヤマボウシ(山法師)の美しさが際立ちます。

ひこばえ
ヤマボウシ(山法師)は、株元からひこばえがよく出てきます。一本立ちのヤマボウシを株立ちに仕立て直す際は、ひこばえを成長させていきます。

太い幹の更新
太い幹を更新する場合は、地際(根元)で切ります。背丈が高い太い幹を切る際は、部分的に落としていきます。庭師や造園専門業者にお任せいただけたらと思います。
ヤマボウシ(山法師)の樹高
 ヤマボウシ(山法師)は、ミズキ科の落葉高木で、樹高が10〜15mほどに成長します。
ヤマボウシ(山法師)は、ミズキ科の落葉高木で、樹高が10〜15mほどに成長します。
成木の樹形は壮麗(そうれい)で、白く開いた白い総苞片(そうほうへん)が美しく、花が咲く4月下旬から5月頃は、景観を一変させる存在感を放ちます。
 庭木の場合、毎年剪定して樹高が高くなり過ぎないように調整していきます。
庭木の場合、毎年剪定して樹高が高くなり過ぎないように調整していきます。
ヤマボウシの剪定時期
ヤマボウシ(山法師)は、枝が横に広がり葉もよく繁ります。自然な枝を生かし自然樹形を保つようにします。
ヤマボウシの剪定時期は、花芽の開花が始まる3~4月を避け、冬の11月~2月頃に行います。特に、落葉している休眠期が適期です。この時期に剪定を行うことで、樹木に与える負担を軽減できます。不要な枝を切り樹形を整え、風通しを良くしておくことで病害虫の発生も防げます。

枝がよく茂る場合は、花後の5月中旬から6月にかけて軽剪定ができる時期です。軽く混み合った枝を間引き、不要枝を整理しておくと、梅雨から夏にかけての高温多湿な環境を軽減できます。

 樹高の調整
樹高の調整
ヤマボウシは屋根を超える高木になります。剪定で低く維持できます。
2階建て住宅の高さは、平均6m~7mで、シンボルツリーの樹高は、3m~4mがバランスが良いとされています。
ヤマボウシは、10mにもなる高木です。ヤマボウシの樹高を抑えるには、芯止め剪定が効果的です。幹を切って新たな枝を誘導し、芯止めを繰り返して高さを調整していきます。
 樹形の乱れ
樹形の乱れ
ヤマボウシを放置していると枝や葉が重なり密集してきます。
もさもさの状態では中に光が届かなくなり、病害虫が発生する要因にもなります。
ヤマボウシの枝を美しく見せるには、少し離れて見たときに向こう側が少し透けて見えるくらいになるように剪定していくのが理想です。
庭木のヤマボウシ
生育範囲が限られているスペースで育てるヤマボウシは、枝を広げすぎないようにします。樹形のバランスが崩れてきたら、切り戻し剪定を行い、高さや広がりを調整します。
(常緑ヤマボウシの植栽)

(枝の広がりを抑えたヤマボウシ)
 |
 |
果実をつけ過ぎないための夏剪定
ヤマボウシ(山法師)は、沢山の花が咲くと同時に沢山の実がつきます。果実が付きすぎると栄養が分散してしまうため、多くつけないためには、花後に軽く間引剪定をします。

ヤマボウシの実の量を調整
 |
ヤマボウシの花が沢山咲いていると見応えもあるのですが、花後に付く果実の量も沢山です。
果実の収穫が目的でないとすれば、花が咲き終わる6月頃に枝を軽く切ることで、実の量を調整できます。 |
 |
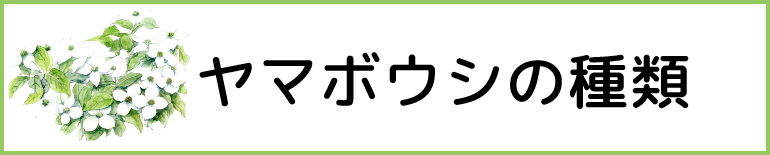
ベニバナヤマボウシ
ベニバナヤマボウシは、ヤマボウシの園芸品種です。淡いピンク色の花(総苞片)が特徴で、日光が当たるとより濃い色になります。
秋には赤い実がなり、紅葉も楽しめ、洋風のお庭にもよく合います。
(洋風の庭に植栽しているベニバナヤマボウシ)


ベニバナヤマボウシの紅葉は、秋(11月頃)に葉が赤く色づきはじめます。
斑入りヤマボウシ
斑入りヤマボウシは、緑とクリーム色の斑(まだら)模様が入った葉が特徴です。
初夏には白い花(総苞)が咲き、秋には赤く実が熟します。紅葉もします。秋の葉はピンクがかったグラデーションのまだら模様です。特に「ウルフアイ」などの品種は、葉がしっかりしていて丈夫で、夏から秋まで斑が消えにくいのも魅力です。成長が比較的ゆっくりで樹形もまとまりやすく育てやすく、洋風のお庭にもよく合います。
(葉の外側が白い「斑入りヤマボウシ」)


斑入りのヤマボウシの葉は、縁(ふち)が華やかで、和風、洋風にも合います。夏に斑が消える品種も多いのですが、特に「ウルフアイ」は夏から秋もきれいな斑色を保つことで知られています。
常緑ヤマボウシ
新しい品種で注目されている常緑性のヤマボウシ「常緑ヤマボウシ」は、一年中葉をつけています。
常緑ヤマボウシにも品種があります。赤い実が付く「ホンコンエンシス」や、実が付かない品種として知られているのは、新種の「赤花常緑ヤマボウシ」です。赤花常緑ヤマボウシは、秋になると赤やピンクの濃いピンク色の花(総苞片)が咲きます。
(冬でも落葉しない「常緑ヤマボウシ」)

 赤い実が付く「ホンコンエンシス」の紅葉は、秋から冬にかけて、赤色に染まり、同じ時期に果実も楽しめます。
赤い実が付く「ホンコンエンシス」の紅葉は、秋から冬にかけて、赤色に染まり、同じ時期に果実も楽しめます。
常緑ヤマボウシの葉は、春になると緑色に戻ります。
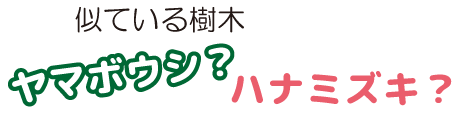
ヤマボウシ(山法師)とハナミズキ(花水木)の違い・見分け方
ヤマボウシには、日本固有の「ヤマボウシ」、アメリカ東海岸地方が原産の「アメリカヤマボウシ」があり、よく似た樹木として知られています。

ヤマボウシとハナミズキの見分け方は、花、葉、実、樹皮などに違いがあります。見分けるポイントは、開花時期です。ハナミズキの開花は、春の4月中旬から5月中旬に花を咲かせます。ヤマボウシは初夏の6月から7月に花が咲きます。
また、花びらに見える総苞片(そうほうへん)の形も異なります。マボウシの総苞片は、先端が尖っています。ハナミズキの総苞片は、先端がくぼんでいます。
実の形にも違いがあり、ヤマボウシの実は、丸く表面がボコボコしています。ハナミズキの実は、楕円形で滑らかです。
ヤマボウシ |
ハナミズキ |
|
 |
 |
|
ヤマボウシの開花時期:5月から7月上旬の間、初夏に咲きます。 |
ハナミズキの開花時期:4月中旬から5月上旬の春に咲きます。 |
|
| ヤマボウシの総苞片(そうほうへん)の先端は、とがっています。 | ハナミズキの総苞片(そうほうへん)の先端は、丸く窪んでいます。 | |
 |
 |
|
| ヤマボウシは高木です。樹高は10~15mにもなります。 | ハナミズキは小高木です。樹高3~4mくらいです。 | |
 |
 |
|
ヤマボウシは、葉が先です。葉の上に花が伸びていきます。 |
ハナミズキは、花が先です。あとから葉が開いていきます。 | |
 |
 |
|
| ヤマボウシの樹皮は、赤褐色でウロコ状に剥がれ、まだら模様です。 | ハナミズキの樹皮は、細かくひび割れた模様の灰褐色です。 | |
 |
 |
|
| ヤマボウシの葉の裏面は、やや光沢があります。 |
ハナミズキの葉の裏面は、粉白色を帯びています。 | |
 |
 |
|
| ヤマボウシの果実は、表面がボコボコとした球体です。 | ハナミズキの果実は、楕円形で枝先に数個集まってつきます。 | |
 |
 |
|
| ヤマボウシのピンク色の品種は、淡く優しい印象です。色の濃淡には個体差があります。 | ハナミズキのピンク色の品種は、華やかさがあります。淡いピンクなど濃淡の種類があります。 |

ヤマボウシの春夏秋冬
ヤマボウシ(山法師)は日本の初夏を代表する花木です。春には若い新緑が芽吹き、初夏には白い花(総苞片)が満開となります。秋には果実が実り収穫でき、鮮やかな紅葉で樹全体を彩ります。落葉性のヤマボウシは冬になると葉が落ち、自然樹形の美しい枝ぶりを観賞できます。
 ヤマボウシの街路樹
ヤマボウシの街路樹
ヤマボウシ(山法師)は四季折々に多彩な楽しみがある花木ですが、街路樹として植栽されているヤマボウシが少なくなっています。
主な理由としては、熟した果実がボトリと丸ごと落下することがあげられます。落ちた実が踏まれた地面は汚れます。秋の台風で落下した実はベトベトになったりと、実の落下時期は掃除が少々大変です。それでも雑木の庭に一際目立つヤマボウシの存在は魅力があります。
ヤマボウシの花が終わると、萎れる総苞片(そうほうへん)
白い総包片(そうほうへん)は花を包んでいた葉で、花びらのように見える部分です。
花は、中心の基部に集まっています。花が咲き終わる頃、白い総包片(そうほうへん)も垂れるように萎れていき、7月にもなると変色して枯れて散っていきます。
(花が終わる頃、萎れはじめる総包片)

低めの位置に長く伸びる枝、花の観賞
ヤマボウシは、10mにもなる高木です。庭のシンボルツリーとして育てる際は3m~4m、大きくなっても5mあたりで調整し、中庭で育てるヤマボウシは定期的に芯止めを繰り返し2m~3m程度の高さに調整していきます。

ヤマボウシと同じ時期に開花している、下に向いて咲く「エゴノキ」のような高木の花は、見上げるように観賞されることが多く、上の方に枝があると花がよく見えます。
(エゴノキの花、ヤマボウシの花)

「ヤマボウシ」の花は、上に向いて伸びます。葉が茂っていると下からは殆ど花が見えなく、低めの位置に長く伸びる優美な枝があると花を観賞できます。
(地植え・庭木のヤマボウシ)

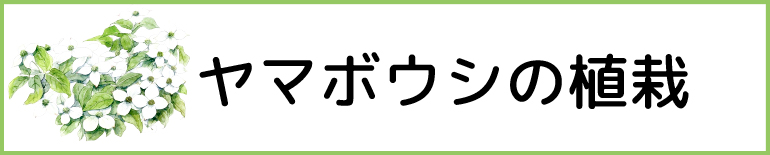
ヤマボウシを育てる場所、適した環境
ヤマボウシは日当たりのよい場所を好みますが、乾燥と多湿に弱く、夏の直射日光があたる場所を避け、風通しの良い明るい半日陰が適しています。
(ヤマボウシの植栽)

植え付けの際には土に元肥を混ぜておくと植物の生育がより良くなります。 植え付け後の若木は、根がしっかりと張るまでの間は、土が乾燥しないよう定期的に水やりをします。
(ヤマボウシがあるお庭)

![]() ヤマボウシが大きくなり過ぎてお困りではありませんか?山崎造園では、高所作業や斜面の剪定も行っております。庭木の植栽、剪定、庭の手入れ、外構工事全般、門柱・アプローチの取り付け工事、駐車場の増設など、お庭リフォームから戸建て住宅の建物周辺、店舗の庭設計・施工までご相談ください。
ヤマボウシが大きくなり過ぎてお困りではありませんか?山崎造園では、高所作業や斜面の剪定も行っております。庭木の植栽、剪定、庭の手入れ、外構工事全般、門柱・アプローチの取り付け工事、駐車場の増設など、お庭リフォームから戸建て住宅の建物周辺、店舗の庭設計・施工までご相談ください。
落葉樹のヤマボウシの植栽、常緑ヤマボウシの植栽、記念樹の植栽、庭木一本から承ります。お庭のことでお困りの際はぜひお声掛けください。
主要地域 :造園工事も対応いたします!
兵庫県宍粟市内(一宮町、山崎町、千種町、波賀町)、姫路市、たつの市、揖保郡、佐用郡、神崎郡、朝来市、福崎町、他
高砂市、加古川市、太子町、相生市、赤穂市、加西市、小野市、加東市、三木市、西脇市、明石市、播磨町、稲美町、市川町、神戸市、他 近畿周辺 )
常緑ヤマボウシの選抜品種

2025.12.08
このヤマボウシは、常緑ヤマボウシの選抜品種「常緑ヤマボウシ(ホンコンエンシス 月光)」です。
選抜品種というのは、特定の形質(特性)を持つ個体を選び出し、生み出された品種のことです。
常緑ヤマボウシの紅葉は、品種や日当たりの状況によって変わりますが、春まで緑とピンクが混ざった色のままであったり、環境によっては葉全体が渋い赤紫色に変わり、冬でも葉がある存在感が素晴らしいです。
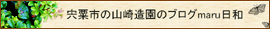 詳しくは山崎造園のブログ「常緑ヤマボウシの選抜品種」の記事で紹介しています。
詳しくは山崎造園のブログ「常緑ヤマボウシの選抜品種」の記事で紹介しています。
見上げる高さのヤマボウシ

2025.05.17
背丈が5mはある立派なヤマボウシです。花姿を撮ろうとしたものの、見上げる枝に向かって手を伸ばして...つま先立ちでようやく撮れたのは横姿でした。
ヤマボウシの花は上に向いて伸びます。下から見上げる姿もよいのですが、花を観賞できる枝垂れる枝がほしい樹木です。
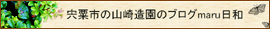 詳しくは山崎造園のブログ「高木になるヤマボウシ(山法師)」の記事で紹介しています。
詳しくは山崎造園のブログ「高木になるヤマボウシ(山法師)」の記事で紹介しています。
シンボルツリーのヤマボウシ(山法師)

2017.05.28
ヤマボウシをシンボルツリーとして店舗の入り口横に植えられているお店です。
「ヤマボウシやね、もう梅雨やね~。」、別の方は「ここのヤマボウシ、枝がキレイやわ~」と、四季の移ろいを楽しまれていました。
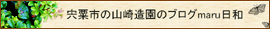 詳しくは山崎造園のブログ「ヤマボウシ(山法師)があるお店」の記事で紹介しています。
詳しくは山崎造園のブログ「ヤマボウシ(山法師)があるお店」の記事で紹介しています。
6月 宍粟市周辺の見どころ
宍粟市は兵庫県中西部に位置し、地域の人々により守り育てられている“豊かな自然”や、
四季折々の花が咲き誇る“花の名所”が各地にあります。
宍粟市に隣接するおすすめ観賞スポットにも是非訪れてください。

摩耶山(まやさん)天上寺
神戸市指定
市民の木「ヤマボウシ」
摩耶山天上寺境内のヤマボウシは、樹齢 約160年で、高さ 約12メートル、兵庫県下でトップクラスの大きさです。 樹形も整っており、県下で1番美しいといわれています。
平成26年4月、摩耶山天上寺境内のヤマボウシが、神戸市指定「市民の木」に認定されました。
「ヤマボウシが市民の木に指定」(神戸市)
・ 場所 : 兵庫県神戸市灘区摩耶山町2-12
・ 開花時期 : 6月の上旬~中旬が見頃です
・ 詳しくは 巨木の純白、山頭で涼しげ 神戸・摩耶山天上寺のヤマボウシ
(2021/6/7 神戸新聞NEXTのホームページ)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|