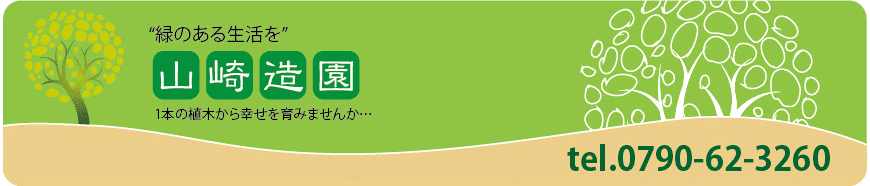トップページ > 庭木・植木のお手入れ・お庭づくりのアドバイス
姫りんご(姫林檎)の害虫
庭植え(地植え)の姫りんごに カイガラムシ が発生!?
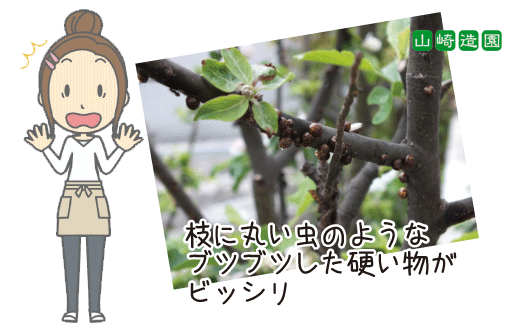

姫リンゴを地植えで育てている個人邸のお庭です。

ご相談の状況
「春すぎに気が付いたのですが、姫りんごの枝に丸い虫のようなブツブツした物がビッシリと付いていました。
取ろうとして触ってみたら、ヽ(゚○゚ ;ヽ)三(ノ; ゚□゚)ノ 、ねっとり糸を引いたようなものや、
硬い殻のようになっているものもありました。増えているように思います…。」
~というご相談でした。
 お話しをお聞きした時、 カイガラムシ(吸汁性害虫) ではないかと思いましたが、状況を見にお伺いしたところやはりそうでした。
お話しをお聞きした時、 カイガラムシ(吸汁性害虫) ではないかと思いましたが、状況を見にお伺いしたところやはりそうでした。

タマカタカイガラムシ(カタカイガラムシ科)は、吸汁性害虫です。
汁を吸って植物に被害を与え、樹を枯らしてしまいます。
土や枝にいる幼虫を徹底的に駆除し、成虫にさせないことです。
見つけたら歯ブラシやタワシを使ってゴシゴシとこすり落とし、薬剤を散布して予防しましょう!
カイガラムシの幼虫
![]() カイガラムシの幼虫は、春から秋まで次々と土中から孵化してきます。木を登り、成虫になったら脚が退化し吸汁します。
カイガラムシの幼虫は、春から秋まで次々と土中から孵化してきます。木を登り、成虫になったら脚が退化し吸汁します。
幼虫はかたい殻に覆われていません。
薬剤散布で効果があります。
しかしカイガラムシは、秋頃まで孵化を続けますので、取ってもまた次々に発生してきます。
根気よく取り除き、定期的に薬剤を散布します。
カイガラムシの成虫
![]() 足の無い硬い殻で覆われているのがカイガラムシの成虫です。枝や幹から汁を吸い、生育に悪影響を与えます。殻(硬い虫体被覆物)に覆われてしまいますので、殺虫剤の浸透も期待できるものではありません。
足の無い硬い殻で覆われているのがカイガラムシの成虫です。枝や幹から汁を吸い、生育に悪影響を与えます。殻(硬い虫体被覆物)に覆われてしまいますので、殺虫剤の浸透も期待できるものではありません。
とにかく今付いている成虫をゴシゴシと刮(こそ)ぎ落とします。
(落としたカイガラムシは、脚が退化しているので登ってきません。植物の組織内に口吻を残してたまま引き剥がすことになりますので、摂食ができず落とせば死にます。)

姫りんごの害虫被害
(写真:7月上旬、茂っている姫りんごに付いている害虫、カイガラムシは年々増えていきます。)
カイガラムシの卵は越冬します。
成虫を落としたあと、予防としては新しい土に植え替えるのも一つの方法です。
暖地では2月下旬から~3月にかけてが植え替えに良い時期です。
土中にいる幼虫がまだ活動をしていない時期に植え替えを行います。
(写真:↑上)枝葉が茂りすぎて混み合っています。風通しを良くするためにも剪定が必要です。

姫りんごの実が付いた木に害虫被害
こちらのお宅でもカイガラムシが発生しました。
(写真:6月下旬、実が付いている姫りんごに害虫被害)
姫りんごの実が付いている頃の剪定
姫りんごは、4月~5月に花が咲き、花が終わったら実が成ります。
姫りんごの剪定は、夏剪定と冬剪定を行います。
姫りんごの「夏剪定」は、実が付き出す頃に行います。枝が込み合い日当たりが悪いとカビが原因で葉が枯れたり病気になったり成長を妨げます。
一度花芽のできた短枝(たんし)は、毎年形成されますので、維持するように(花芽を切らないように)注意して枝を整えていきます。
(※全体の剪定は、落葉後(12月~来3月下旬くらいまで)に行いますので、夏剪定は茂った葉が蒸れないように風通しをよくする程度にとどめておきます)
カイガラムシ(吸汁性害虫)は、風通しの悪い環境で発生しやすい害虫です。
カイガラムシは秋頃まで孵化し続けます。
ゴシゴシとり落とすのは気の遠くなるような作業になりますが、何もしないままではカイガラムシは来年も現れます。
姫りんごの剪定
花付き、実付き・枝ぶりを良くするため、害虫予防にも剪定は欠かせません!
 姫りんご(姫林檎)の剪定は、冬季(12~3月)と夏季(6月頃)に行います。
姫りんご(姫林檎)の剪定は、冬季(12~3月)と夏季(6月頃)に行います。
春から初夏に長卵形の葉をつけます。植えつけて3~4年すると枝の成長を整えていきます。

姫りんご 夏季剪定
(写真:7月中旬ころ、夏の姫りんご)
夏は葉が茂ります。
剪定は、枝同士が重なり合う交差枝や、徒長枝(とちょうし)を切るぐらいに留めておきます。
姫りんご 冬季剪定
姫りんご(姫林檎)は冬に葉が全部落ちます。
庭植え(地植え)の場合、落葉後12月~(翌3月くらいまで)、
芽が動き出す前に剪定をします。
幹や太い枝から上方に向かって伸びる徒長枝(とちょうし)を剪定します!全体の樹姿(樹形)をイメージして伸び過ぎている枝を整えていきます。
成長して高くなり、落葉でご近所に迷惑にならないように成長を整えます。
花芽が付かず樹形を乱す枝 「徒長枝」(とちょうし)
枝には、葉が付いていない長枝(ちょうし)と、花芽や実が付く短枝(たんし)があります。
姫林檎は短枝(たんし,先端にある節)に花が付きます。
徒長枝(とちょうし)は、太い幹や枝の中途から勢いよく伸びている枝です。
樹形を乱すだけでなく花芽も付きにくい枝です。
放置しているとこの枝に養分が取られ他の枝の成長に影響したり、樹形が乱れる要因になります。
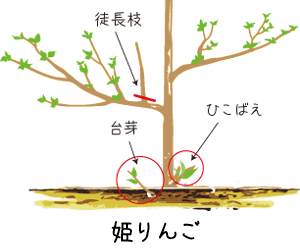
芽吹きも行いましょう。
姫りんごは、ひこばえや台芽が出やすいです。
台芽(だいめ)は、株の付け根や地中の根、台木から出る芽です。
ひこばえは、太い幹に対して出る芽で、孫(ひこ)に見立てて「ひこばえ(孫生え)」といいます。
樹木が地面と接する地際(じぎわ)のところを見ます。
根もとから出てくる枝は台木から出ていることが多く、
根元よりかき取ります。そのままにしておくと栄養がこの枝に集中してしまい(他の枝に行き渡らず)
枯れてしまうケースがあります。
ひこばえや台芽を見つけたら取り除く習慣を付けましょう。
カイガラムシの取り除きは根気のいる作業です。
山崎造園では、剪定が困難な斜面や高所作業も行います。薬剤散布や肥料やり・土の入れ替えなど、姫りんごの剪定についてもお気軽にご相談ください。
主要地域 :造園工事、お庭のリフォームも対応いたします!
兵庫県宍粟市内(一宮町、山崎町、千種町、波賀町)、姫路市、たつの市、揖保郡、佐用郡、神崎郡、朝来市、福崎町、他
高砂市、加古川市、太子町、相生市、赤穂市、加西市、小野市、加東市、三木市、西脇市、明石市、播磨町、稲美町、市川町、神戸市、他 近畿周辺 )
 『 カイガラムシ駆除から一年後 』
『 カイガラムシ駆除から一年後 』
2017.05.29
昨年の今頃。「タマカタ カイガラムシ」が大量発生した姫りんごのお宅に、今年も伺いました。
カタカイガラムシは主にバラ科の植物(サクラやウメ、アンズやスモモ、リンゴなど)に発生します。
卵から孵化したばかりの幼虫には脚がありますが、成虫は球形のかたい殻に覆われています。 脚がなく、赤味を帯びた色に暗褐色の横長の紋があるのも特徴です。樹液を吸って成長します。
あれから一年。「姫りんご」のその後、今年の様子です。
葉のウラの裏まで、枝の隅々まで見ましたが、カイガラムシはいませんでした!! ♪
。:.゚ヽ(*へへ)ノ゚.:。+゚
本当に一匹もいません!
去年駆除する際、枝をかなり透きました。今年は風通しも良く向こうが見えています!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|