トップページ > 季節の花・ガーデニングを楽しむ
11月 ヒイラギ(柊)
 ヒイラギ(柊)は、モクセイ科の常緑小高木です。
ヒイラギ(柊)は、モクセイ科の常緑小高木です。
ヒイラギ(柊)は、冬の花。木 に 冬 と書いて 『 柊 』 です。
10月下旬頃から~12月頃に、白い小さな花がかたまって咲きます。
ヒイラギ(柊)の葉・ギザギザ
 ヒイラギ(柊)の葉は、厚く表面が暗緑色で光沢があり、縁(ふち)はギザギザの鋸歯(きょし)があります。
ヒイラギ(柊)の葉は、厚く表面が暗緑色で光沢があり、縁(ふち)はギザギザの鋸歯(きょし)があります。
若木の葉は、鋸歯の先端が鋭い棘(とげ)になっていますが、老木になるほど鋸歯(きょし)が浅くなり丸くなっていきます。

柊(ヒイラギ)の植栽
ヒイラギ(柊)の葉はギザギザで、触ると痛いほどの棘(とげ)があるのも特徴です。
玄関先に “鬼門除け” で植えられることも多く、
昔から“庭の表鬼門(北東)にヒイラギ、
裏鬼門(南西)にナンテンを植えると、鬼門除けになる”という言い伝えから
、災いや厄を避ける植物として古くから親しまれています。
ヒイラギ(柊)と似た花
ヒイラギの花姿は、「金木犀」や「柊木犀」と似ていて、花だけを見ると混合されがちですが、咲き出す時期が少し違い、金木犀や柊木犀の後に咲くのが柊(ヒイラギ)です。
 |
 |
|
オレンジ色の小さい花が沢山つきます。 金木犀(キンモクセイ) |
白い小さな花がたっくさん付きます。 銀木犀(ギンモクセイ) |
 |
 |
|
ヒイラギとギンモクセイの交雑種です。 柊木犀(ヒイラギモクセイ) |
白い小さな花が11月頃に咲きます。 柊(ヒイラギ) |
ヒイラギ(柊)の実
 |
ヒイラギ(柊)は、青い実が付きます。
|
 |
赤い実が付くのは、セイヨウヒイラギ(西洋柊)です。クリスマスリースなどの装飾用として使われているヒイラギは
『セイヨウヒイラギ(西洋ヒイラギ)』といってモチノキ科です。秋が深まる11月ごろから赤い実を付けます。 |
どちらも「ヒイラギ」という名が付いていますが別種です。
ヒイラギの生垣・庭木
ヒイラギは、一年中葉が緑色をした常緑性です。葉のギザギザに当たると痛く、防犯として生垣にもよく使われています。老木になると縁(フチ)の刺(トゲ)がなくなって、丸い葉の形に近くなっていきます。
 ヒイラギの生垣
ヒイラギの生垣
モクセイ科のヒイラギ(柊)は常緑性の小高木です。1本の大きな木に育てることもできますが、戸建て住宅では垣根・生垣に使われることが多いです。
枝が上や下向き内側など色んな方向に生え樹形が乱れていきますので剪定で整えていきます。
 玄関横やアプローチの植栽に、赤い実のヒイラギモチがよく映えます。
玄関横やアプローチの植栽に、赤い実のヒイラギモチがよく映えます。
(写真:「ヒイラギモチ」(チャイニーズホーリー)
ヒイラギモチの葉は四角張ったギザギザで、冬は赤い実が付き、春は白い花が咲きます。 クリスマス・ホーリーと混合されているほど似ています。常緑低木です。

西洋ヒイラギは生垣・庭木向き
(写真:クリスマスホーリー(西洋ヒイラギ)
リースなどの装飾用として利用される赤い実が付くクリスマスホーリー(西洋ヒイラギ)も常緑性の低木ですが、枝の伸び方が横より上方向(縦)に育つ(伸びる)性質があります。樹木を植え並べるような「生垣に適しています。

(写真:ヒイラギの植栽)
育ち過ぎたヒイラギ(柊)の剪定、高所作業や斜面作業などクレーンを使った手入れも行っております。
11月 宍粟市周辺 花の見どころ
「宍粟市」は兵庫県中西部に位置し、地域の人々により守り育てられている“豊かな自然”や、 四季折々の花が咲き誇る“花の名所”が各地にあります。
六甲山に行ってみよう!
神戸市立森林植物園

神戸市立森林植物園(1940年に開館)は、四季折々の自然を丸ごと体感できる六甲山の自然を活かした総面積142.6haの広大な植物園です。
ヒイラギの花は見本園内、コナラ広場のすぐ近くで見ることができます。
森林植物園のいま ヒイラギ
・ 場所 : 神戸市北区山田町上谷上字長尾1-2
・ 詳しくは→ 森林植物園の花・緑情報 「ヒイラギ」
(森林植物園のホームページ)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
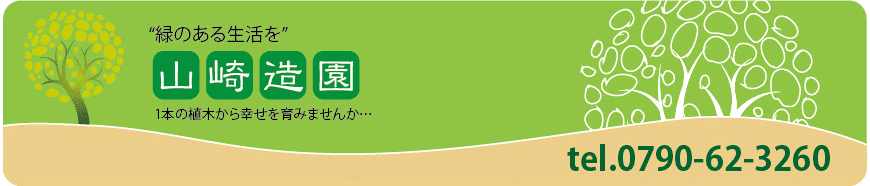

































 ヒイラギ(柊)の花
ヒイラギ(柊)の花